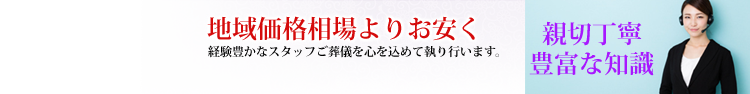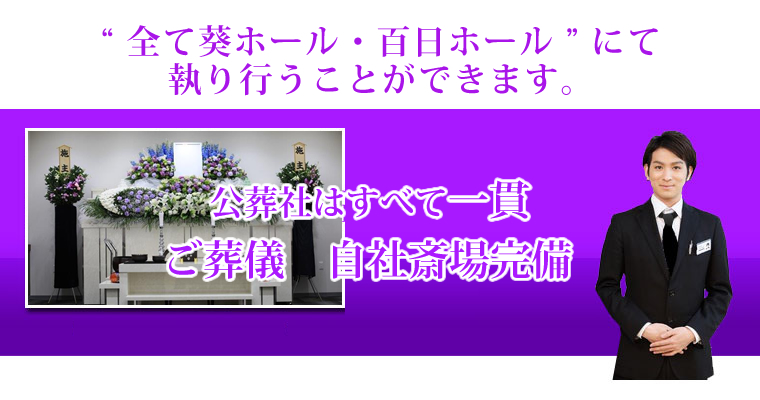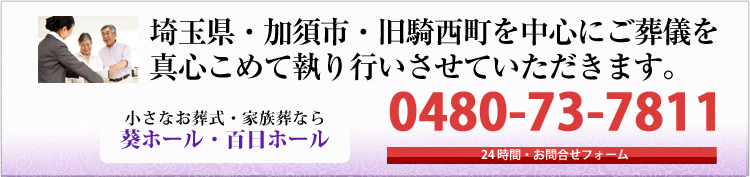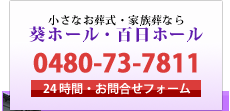「故人様の想い」「ご遺族の想い」を大切にします
時代とともに多様化するお葬式。
とはいえ、お葬式は大切な人との最後のお別れの儀式です。
そのような大事な時間のお手伝いをさせて頂くとき、公葬社が考えるのは、「故人様らしさ」と「ご遺族の想い」です。
故人様がお好きだったお花、食事、趣味など…様々な故人様らしさをお葬式の中で表現し、ご遺族とともに最後のときを、忘れられない思い出の時間になるよう、
心をこめて精一杯お手伝いをさせていただきます。
- 流れ
- 喪家側が行うこと
- 危篤
- ●近親者、親しい友人に連絡
- 御臨終
- ●清拭と死化粧
●寺院に連絡
●公葬社に連絡
●御自宅または葬儀の式場へ遺体の搬送
- 御葬儀の準備
- ●喪主の決定
●葬儀の方針を決定
●公葬社と打ち合わせ
●御葬儀の日程の決定
●親族・友人・知人・勤務先への御連絡
●死亡届の提出
●式場の準備
●手伝いの依頼
●納棺
●喪服の準備
- 御通夜
- ●僧侶の接待
●通夜ぶるまい、喪主などのあいさつ
●僧侶や互助会・葬祭業者と葬儀の打ち合わせ
- 御葬儀
- ●席順、準備の確認
●喪主などのあいさつ
●会葬礼品の用意
●御出棺
- 火葬
- ●火葬場へ
●拾骨
●留守番の人は遺骨迎えの準備
- 直後の儀礼
- ●還骨勤行、初七日法要
- 御会食
- ●精進落とし
●手伝いをねぎらう
●係からの引き継ぎ
- 御納骨
- ●墓所を入手
●納骨
- 忌明け
- ●四十九日法要
●香典返し
●後かたづけと形見分け